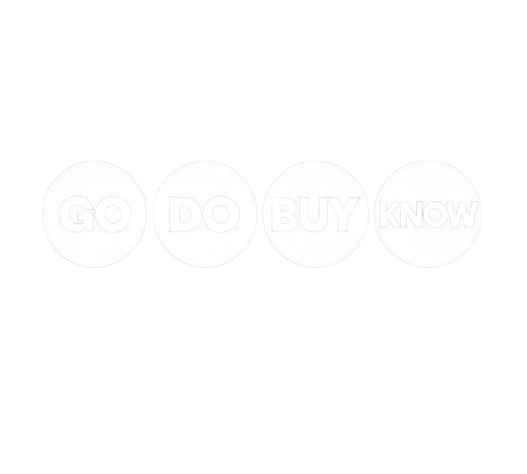固定電話をあまり使わなくなった今、「固定 電話 やめて よかった」と感じる人が増えています。一方で、いざ解約を検討すると、「本当に後悔しないか」「手続きは面倒ではないか」と不安になる方も少なくありません。特に、NTTの電話加入権がなくなるとどうなるのか、加入権の名義確認方法はどうするのかといった疑問はよく聞かれます。
この記事では、固定電話をやめたことで感じるメリットを中心に、解約によって発生するデメリット・困ること、さらには解約後に「繋がる・請求がくる」といったトラブルについても詳しく解説していきます。また、解約によって銀行の手続きに影響は出るのか、インターネットはどうなるのか、引き込み線は撤去が必要なのかなど、気になる点を一つひとつ整理していきます。
そのほかにも、解約によっていくら戻るのか、本人が死亡した場合や本人以外が手続きをするにはどうすればよいか、工事の立会いは必要なのかといった実務的な疑問にも触れていきます。「固定電話をやめたいけど迷っている」という方にとって、後悔のない判断ができるよう、わかりやすく丁寧に情報をお届けします。
※本記事はPRを含みます。
- 固定電話をやめた場合のメリットとデメリット
- 解約に伴うトラブルや注意点
- 電話加入権や名義の扱い方
- 解約後のインターネットや銀行手続きへの影響
固定電話をやめてよかったと実感できる理由
- 解約した場合のデメリット・困ることを正しく理解する
- 固定電話を解約した人の後悔の声は本当に多い?
- 解約した場合インターネットはどうなるのか?
- 解約した引き込み線の撤去は必要か?
- 解約の際の工事立会いの有無について
- 電話加入権とはどんな権利?
- NTTの電話 加入権がなくなると一体どうなるか
- 電話加入権名義の確認方法を解説
- 解約は本人死亡・本人以外が手続きするには
- 固定電話 解約したのに繋がる・請求がくる場合
- 解約すると銀行手続きに影響はあるのか?
- 固定電話を解約するといくら戻るのか?
- 固定電話の機能をどうしても残したい場合は?リスト
解約した場合のデメリット・困ることを正しく理解する

固定電話を解約する前には、メリットだけでなく「どんなデメリットや不便があるのか」を正しく把握しておくことが大切です。たしかに固定電話を使わない家庭では、解約によって無駄な支出を減らすことができますが、何も考えずに解約してしまうと予想外の困りごとが発生する可能性もあります。
まず注意しておきたいのが、FAXの使用ができなくなることです。自宅でFAX機能を使っている場合、固定電話がなくなるとそのままFAX機器が使えなくなります。特に仕事や地域活動などでFAXの送受信が必要な場面がある人にとっては、不便を感じる場面もあるでしょう。
また、登録していた電話番号の変更手続きが必要になることもあります。たとえば、クレジットカード会社、保険会社、学校、勤務先などに固定電話番号を登録していた場合、そのすべてを携帯電話番号に変更しなければなりません。変更漏れがあると、大切な連絡が受け取れないことにもつながりかねません。
さらに、災害時や緊急時の連絡手段が減るという点も見逃せません。アナログの固定電話は、電源が不要なモデルであれば停電時でも通話が可能な場合があります。一方で、携帯電話やIP電話は電源や回線状況に左右されるため、災害時に必ずしも安定して使えるとは限りません。このような背景を踏まえると、固定電話を解約する際には、自宅の防災体制や家族構成も含めて慎重に判断する必要があります。
こうして整理してみると、固定電話には「使わないなら解約で問題ない」という単純な判断では済まない、生活に密接に関わる側面があることがわかります。解約によるメリットとデメリットの両面を把握した上で、自分のライフスタイルに合った選択をしていくことが求められます。
固定電話を解約した人の後悔の声は本当に多い?

固定電話をやめたことで「後悔した」という声は一部に見られますが、実際にはそれほど多くないのが実情です。むしろ、解約後に困ることはほとんどなかったという声が主流であるとも言えます。
例えば、固定電話を解約した人の多くは「そもそも数年間一度も使っていなかった」「営業電話や詐欺電話が減って安心できた」といった前向きな感想を持っています。スマートフォンの普及により、日常的な連絡手段としての役割がほぼスマホに置き換わっている現在では、固定電話を持ち続ける理由が薄れてきているのです。
一方で、「後悔した」という意見に多いのは、古くからの知人や親族との連絡が取りにくくなったという点です。特に年配の親戚や、昔の友人などには携帯番号を伝えていないケースも多く、そうした相手が旧来の固定電話番号にしか連絡できなかったということもあります。突然連絡手段が断たれたように感じられ、結果として疎遠になってしまうケースもあるようです。
また、信用審査などで固定電話番号が求められた経験がある人も、後悔の声をあげています。特に以前の賃貸契約やローン申請などでは、固定電話番号を記入することが信頼性の証として扱われることがありました。もっとも、現在ではそのような場面も減ってきており、多くの金融機関やサービスが携帯電話の番号だけで対応できるようになっています。
このように、「後悔した」という声がゼロではないものの、それらは固定電話の利用頻度や家庭の事情によって変わるものです。総合的に見ると、現在の通信環境では固定電話がなくても日常生活に大きな支障はないケースが大半であり、後悔の声は限定的であると考えてよいでしょう。
解約した場合インターネットはどうなるのか?

固定電話の解約を考えたとき、「インターネット回線まで使えなくなるのでは?」と不安に思う方は少なくありません。しかし、実際には固定電話を解約しても、現在主流となっている光回線やケーブル回線などのインターネット回線はそのまま使い続けることが可能です。
ただし、注意すべき点もあります。まず、アナログ回線やADSLなど、かつてのインターネット接続方法では電話回線とネット回線がセットになっているケースが多く見られました。このようなタイプの契約では、固定電話を解約するとインターネットも同時に停止してしまう可能性があります。しかし、ADSLなどの旧式回線はすでにサービス終了している場合が多いため、現在の新しい契約であれば基本的に問題はありません。
一方で、光回線とひかり電話をセットで契約している場合には少し注意が必要です。光回線自体は継続可能ですが、オプションとして利用している「ひかり電話」のみを解約する際には、契約プランの変更や料金体系に影響が出る可能性があります。たとえば、セット割引が適用されていた場合、割引が外れてインターネット料金が若干上がることもあるため、事前に契約内容を確認しておくと安心です。
また、契約しているプロバイダーによっては、電話サービスの契約と一緒にネット回線が提供されているケースもあるため、プロバイダー側に「電話だけを解約したい」という意向をしっかり伝え、解約に伴う影響を確認しておくことが重要です。このように、固定電話を解約してもインターネットは継続利用できますが、契約状況によっては手続きや料金の見直しが必要になることもあります。固定費削減のために解約を検討している場合には、回線やオプションサービスの構成を正しく理解してから進めることが、安心して手続きするポイントです。
解約した引き込み線の撤去は必要か?

固定電話を解約した後、自宅に引き込まれていた電話線(引き込み線)をそのまま残すかどうかは、多くの方が迷うポイントです。結論から言えば、引き込み線の撤去は必ずしも必要ではありません。しかし、撤去すべきかどうかは状況によって異なりますので、自宅の環境や将来の予定を考慮して判断することが大切です。
そもそも引き込み線とは、電柱から自宅に引き込まれている電話回線のケーブルのことです。この線を通じて固定電話の通話が可能になっているわけですが、解約後も物理的にはそのまま残るケースがほとんどです。NTTなどの通信会社は、解約時に引き込み線を自動で撤去するわけではないため、撤去を希望する場合は別途手続きを行う必要があります。
撤去が必要となる代表的なケースは、建物を売却する予定がある場合や、管理会社から原状回復を求められている場合です。特に賃貸物件では、室内外のケーブル類について「元の状態に戻してください」と指示されることもあります。このとき、引き込み線の撤去費用は自己負担になる場合があるため、あらかじめ見積もりをとっておくと安心です。
また、見た目をすっきりさせたい、不要な配線を減らしたいという理由で撤去を希望される方もいます。とくに壁や天井の配線が気になる方にとっては、引き込み線の撤去で室内がすっきりするというメリットがあります。
一方で、将来的に固定電話を再契約する可能性がある場合は、引き込み線を残しておく方がコスト面で有利です。再び電話回線を利用する際に、新たに配線工事が必要になると、数千円から数万円の費用が発生することもあります。そのため、再利用の可能性が少しでもあるなら、あえて撤去しない選択も十分合理的です。
このように、引き込み線の扱いには明確な「正解」はなく、それぞれの事情に応じて判断する必要があります。撤去するかどうかを決める際には、現在の住環境や将来の使い道、費用負担などを総合的に考えることが重要です。
解約の際の工事立会いの有無について

固定電話を解約する際、「工事の立会いが必要になるのでは?」と心配される方も少なくありません。ですが、実際には多くのケースで立会い工事は不要です。とくにNTTの加入電話を解約する場合には、電話やインターネットからの申請だけで手続きが完結することがほとんどです。
具体的には、固定電話を利用していた契約者がNTT東日本または西日本に解約の申し込みを行い、指定された日付でサービスが停止されるという流れです。この手続きにあたって、室内の工事や作業員の訪問が発生することは基本的にありません。そのため、スケジュール調整や立会いの準備をする必要もなく、スムーズに解約できるのが一般的です。
ただし、例外も存在します。たとえば、電話番号を利用休止にする場合や、メタル回線(アナログ・ISDN)を完全に撤去したい場合には、屋外または建物内の配線作業が必要となることがあります。このようなケースでは、立会いを求められる場合があるため、事前に案内される内容をよく確認するようにしましょう。
また、オフィスや集合住宅など、MDF室(主配線盤)やIDF室に接続されている配線を撤去するケースでは、建物管理者の立会いが必要になることもあります。このような建物内工事は専門的な作業を伴うため、立会い日を事前に調整し、MDF室の鍵の手配なども行わなければなりません。
一方で、「ひかり電話」や「おうちのでんわ」などのサービスを解約する場合は、電波や光回線を利用しているため、機器の返却などはあっても立会い工事が求められることはほとんどありません。機器の設置や取り外しもユーザー自身で完了できる簡単な作業です。このように、基本的には固定電話の解約に立会い工事は不要ですが、例外もあるため、自身の契約内容や利用環境をしっかり確認することが大切です。事前にサポート窓口に問い合わせておくことで、不要なトラブルや手間を避けることができます。
固定電話をやめてよかったと感じるための手続き
電話加入権とはどんな権利?

電話加入権とは、固定電話を設置するために必要な「権利」のことを指します。これは、NTTが提供する固定電話サービス(いわゆる加入電話)を利用する際に必要となるもので、「施設設置負担金」として約39,600円(税込)を一度支払うことで得られるものです。つまり、利用者はこの費用を支払うことで、電話回線を敷設してもらうための権利を取得することになります。
この制度は、もともと電話回線を敷設するための費用を、利用者が一部負担するという形で成り立っています。加入権を持っていることで、月々の基本料金が安くなるというメリットもあり、長期的に使う方にとってはコストの抑制につながる仕組みです。
たとえば、法人がオフィスに代表番号を設ける場合などは、信頼性やコスト面から電話加入権を伴う固定電話を導入することがあります。家庭用でも、かつては「固定電話を持っている=社会的信用がある」という考えが強く、特に賃貸契約やクレジットカードの審査において、固定電話番号が求められることがありました。
ただし近年では、インターネットを利用した「ひかり電話」や「IP電話」など、電話加入権が不要なサービスが主流になりつつあります。これにより、電話加入権の必要性は減少していますが、それでも一部のユーザーにとっては重要な資産と認識されているのが現状です。
電話加入権は「物」ではなく「権利」であるため、中古での売買や相続、名義変更なども可能です。したがって、不要になった場合は処分するだけでなく、第三者に譲渡したり、相続の対象にするなどの対応が必要となる場合もあります。
NTTの電話 加入権がなくなると一体どうなるか
NTTの電話加入権が制度として廃止された場合、最も影響を受けるのは、すでに権利を保有している個人や法人です。長年にわたり「資産」として扱われてきた加入権が、ある日突然無価値になってしまう可能性があるからです。
電話加入権は、加入電話の開通に必要な権利として、かつて多くの人々が費用を支払い取得してきました。これが制度として終了すると、その権利の役割がなくなり、実質的に資産価値を失います。つまり、将来的に売却したり相続したりすることができなくなるということです。
NTTは、加入権に対して返金対応を行っていないため、廃止後に何らかの補償がある可能性も非常に低いと言えます。例えば、ある方が昔に約4万円で加入権を購入していたとしても、その権利が制度上消滅してしまえば、その金額は戻ってこないのが現実です。
また、この変化は市場にも波及します。現在、電話加入権を扱っている買取業者やリサイクル市場も、制度廃止とともにそのビジネスの存続が難しくなる可能性があります。なぜなら、取引の対象となる「権利」自体が消失してしまうからです。
とはいえ、IP網への移行が進む中で、制度の役割が縮小しているのは確かです。すでに「ひかり電話」やモバイル通信に移行している世帯では、電話加入権の有無が日常の利便性に影響を与えることはほとんどありません。
このように、NTTの電話加入権がなくなるという動きは、資産価値の消失、買取市場の終息、そして古い制度からの脱却という複数の影響を伴う大きな転換点となります。もし自宅に使っていない電話加入権が残っているようであれば、今後どう扱うかを事前に検討しておくと良いでしょう。
電話加入権名義の確認方法を解説

電話加入権が誰の名義になっているかを確認したい場合、NTTに問い合わせることで簡単に調べることができます。この手続きは特に、相続や名義変更、売却を検討しているときに重要になります。
名義の確認方法としては、まずNTTの「116」へ電話をかけるのが一般的です。固定電話からであれば局番なしの116、携帯電話からであれば地域に応じた専用番号にかけることができます。電話口では、契約者名や電話番号、設置場所の住所などを伝えると、担当者が名義の確認をしてくれます。
また、最近ではNTT東日本や西日本の公式サイトから手続きを進められる場合もあります。本人確認書類を求められることがあるため、免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどを手元に用意しておくとスムーズです。
ただし、名義確認にはいくつかの注意点があります。まず、現在の契約内容や契約者情報が古くなっていると、確認に時間がかかることがあります。とくに長期間使っていなかった回線や、引っ越しなどで実態がわからなくなっている場合は、追加の情報提供を求められることもあります。
また、相続や譲渡を前提に名義を確認する場合には、戸籍謄本などの提出が必要になるケースもあります。この場合は名義人が亡くなっていることを示す戸籍の写しや、相続関係を証明する書類が求められます。電話加入権を正しく管理し、無駄な費用や手間を避けるためにも、名義の確認は定期的に行っておくことをおすすめします。特に、名義人本人以外が解約や譲渡などを行う場合には、あらかじめ確認と書類の準備をしておくと、後の手続きがスムーズです。
解約は本人死亡・本人以外が手続きするには

契約者本人が亡くなった場合や、何らかの理由で本人以外が解約手続きを行う必要があるときは、通常の解約とは異なる対応が求められます。この場合、NTTでは「名義変更」や「相続手続き」を前提とした対応を行っており、いくつかの必要書類を用意して手続きを進めることになります。
まず、契約者が亡くなった場合には、その固定電話の「電話加入権」も相続財産の一部として扱われるため、相続人が手続きを行うことになります。このとき必要となる主な書類は以下の通りです。
- 契約者が亡くなったことを証明する戸籍謄本(コピー可)
- 相続関係を証明できる戸籍謄本(コピー可)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証などのコピー)
- 相続人の印鑑(認印で可)
これらの書類をそろえた上で、NTT東日本またはNTT西日本の指定窓口へ郵送することで名義変更や解約の手続きが可能になります。エリアによって郵送先が異なるため、公式サイトで確認した上で送付しましょう。
一方で、本人が存命でも高齢や入院などで手続きができない場合、代理人による解約も可能です。この場合も委任状や本人確認書類、代理人の身分証明書が必要になります。代理手続きを希望する場合は、事前にNTTへ連絡して詳細な流れを確認しておくと安心です。
このような特別なケースでは、書類の不備や名義確認の不一致などで手続きに時間がかかることもあります。特に、長期間使用していなかった回線や、旧姓・転居などで登録情報が変わっている場合には注意が必要です。
初めて手続きを行う場合には、事前にNTTのサポート窓口に相談し、必要な書類や送付方法を確認しておくことでスムーズに進めることができます。万が一に備えて、家族で加入状況や名義を日頃から把握しておくことも大切です。
固定電話 解約したのに繋がる・請求がくる場合
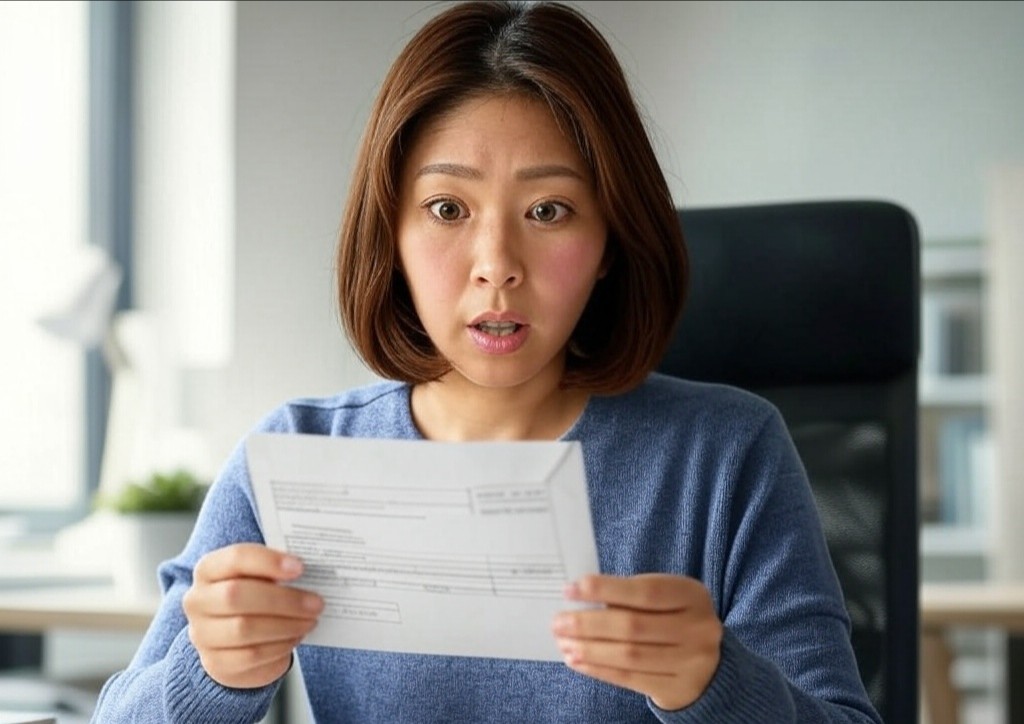
固定電話をすでに解約したはずなのに、回線がまだ繋がっていたり、請求書が送られてきたりすることがあります。このような事態が起きる理由は、主に「手続きが完了していない」「解約が予約状態になっている」「付帯サービスが解約されていない」などが考えられます。
まず確認すべきなのは、解約の完了通知を受け取っているかどうかです。NTTでは解約手続きの受付後、「予約完了メール」や「手続き完了メール」が送信される仕組みになっています。これらのメールが届いていない場合は、そもそも解約手続きが完了していない可能性があります。
また、解約が「即時」ではなく、「予約解約」となっている場合もあります。これは、解約申請はしたものの、実際の停止日が数日〜数週間先に設定されているケースです。その間に通話が可能であることもあり、「まだ使えるのに請求も来た」と感じてしまう原因になります。
さらに、インターネットやFAX、警備システムなどの付帯サービスが解約されていないことも要因の一つです。たとえば、ひかり電話と同時に契約していた「プロバイダ」や「ルーターのレンタル料」などが継続課金されている場合には、固定電話本体の解約だけでは請求が止まらないこともあります。
こうしたトラブルを防ぐには、解約手続きの際に「すべてのサービスを一括で停止する」ように確認することが大切です。また、請求書の明細を細かくチェックして、どのサービスの料金が発生しているのかを把握しましょう。
もし不要な請求が続いているようであれば、NTTのサポートセンターに連絡し、契約内容の詳細や解約状況を確認するようにしましょう。その際、契約者の氏名・電話番号・住所などを準備しておくとスムーズです。このように、固定電話の解約後も何らかの理由で「繋がっている」「請求が来る」と感じることは起こり得ますが、冷静に手順を踏めば対処可能です。早めの確認と、サービス全体の把握が重要になります。
解約すると銀行手続きに影響はあるのか?
固定電話を解約する際、気になるのが銀行や金融関連の手続きに影響が出るかどうかという点です。実際には、最近の多くの金融機関では携帯電話番号を連絡先として登録できるため、固定電話がなくてもほとんどの手続きは問題なく進められます。ただし、例外的に固定電話番号を登録していたまま変更していない場合には、いくつかの注意点が出てきます。
例えば、クレジットカードの本人確認や、口座開設時の本人連絡先として「固定電話の番号」が登録されているケースです。この場合、銀行側から確認の電話がかかってきた際に「すでに使われていない」と判断されてしまうと、連絡が取れないことで一時的な取引停止になる可能性もゼロではありません。
このようなことを防ぐためには、固定電話を解約する前に、金融機関・カード会社・保険会社などに登録している連絡先を一度確認し、必要に応じて携帯電話番号へ変更しておくことが大切です。ほとんどの金融機関ではオンラインバンキングやアプリから手続きが可能なので、それほど手間はかかりません。
また、まれに固定電話番号があることで社会的な信用の一部として扱われていた時代の名残が残っているケースもありますが、現在ではその傾向は大幅に薄れてきています。特に都市部においては、固定電話を持たない家庭や個人が増えているため、固定電話の有無による不利はほとんど見られません。
一方で、高齢の方が多く利用している一部の地銀や信金などでは、引き続き固定電話番号を基本の連絡先として扱っている場合もあるため、該当する場合は個別に相談しておくと安心です。解約する前に一通りの確認と連絡先の更新をしておくことで、万が一のトラブルを防ぐことができます。
固定電話を解約するといくら戻るのか?
固定電話を解約した際、「払い戻し」や「返金」があるのではと期待する方もいるかもしれません。しかし、NTTの固定電話サービスにおいては、基本的に施設設置負担金(電話加入権)の返金は行われていません。つまり、解約してもお金が戻ってくるケースはほとんどないというのが現状です。
そもそも、電話加入権は固定電話を契約するための「権利」であり、いわば初期投資のようなものです。この権利は一度購入すればずっと使えるものの、使わなくなったからといって返金される対象にはなっていません。NTT側もこの点を明確にしており、施設設置負担金は「返金の対象外」とされています。
ただし、まったく無価値になるかといえばそうとも限りません。現在でも中古の電話加入権を取り扱っている一部の業者や金券ショップでは、条件次第で数千円程度で買い取ってもらえる場合があります。相場としては1,000円~6,000円前後とされていますが、実際に査定額がつくかどうかは加入権の状態や市場の動向によります。
なお、NTTの回線を「利用休止」や「一時中断」の状態にすれば、将来的に再利用する際に新たな加入権を買う必要がなくなるため、資産を保持する意味では効果があります。この方法を選べば、すぐに現金が戻ってくることはないものの、結果的にコスト削減につながることもあります。
このように、固定電話の解約で「いくら戻るのか?」という問いに対しては、「基本的には戻らないが、中古市場での売却という選択肢はある」と覚えておくとよいでしょう。金銭的なリターンを期待するよりも、毎月の基本料金が不要になる点をコスト面でのメリットと捉えるほうが現実的です。
固定電話の機能をどうしても残したい場合は?

「固定電話をやめたいけど、電話番号は残しておきたい」「高齢の親が使い慣れているので形だけでも固定電話が必要」というような場合、完全に解約する以外にも方法があります。固定電話のような機能を持ちながら、コストを抑えて継続利用できる手段を選ぶことで、無理なく便利さを維持することが可能です。
具体的には、「おうちのでんわ」などのIP電話サービスが選択肢に挙げられます。これは、携帯電話の電波やインターネット回線を使って、固定電話と同じように通話ができるサービスです。工事不要で、自宅にある電話機をそのまま使えるケースも多く、電話番号の引き継ぎにも対応しています。
こうしたサービスは月額料金が非常に安く、場合によってはキャンペーンによって数百円程度で運用できることもあります。NTTの従来型固定電話と比べて通話料金も割安で、営業電話などもオプションでブロックできるなど、利便性も高くなっています。
また、「ひかり電話」など、光回線に付随するIP電話サービスも選択肢の一つです。こちらはインターネット回線を活用するため、通話品質が安定しており、番号の持ち運び(番号ポータビリティ)にも対応しています。長電話が多い家庭や事業者にも適しており、導入ハードルも低くなっています。
もし、どうしても電話番号を残しておきたいが頻繁には使わない場合には、「利用休止」という手続きを検討してもよいでしょう。これは加入権を維持したまま利用を一時停止する方法で、最大10年間番号を保存しておくことができます。このように、「完全に解約する」ことだけが選択肢ではありません。現代の通信環境に合わせて、より合理的で使いやすい形で固定電話の機能を残すこともできるのです。用途や家庭の事情に応じて、適切な代替手段を選ぶことで、負担を減らしつつ安心を得ることができるでしょう。
総括:固定電話やめてよかったと納得できる理由のまとめ
固定電話やめてよかったと納得できる理由についてまとめます。
- 固定電話の基本料金が不要になり家計が軽くなる
- 営業電話や迷惑電話がほぼ来なくなる
- 使っていなかったFAX機器を処分できる
- 電話加入権の扱いを見直すきっかけになる
- 固定電話番号の名義確認が必要になる場面がわかる
- 古い電話番号に頼らず連絡先を一本化できる
- 停電時の通信手段を見直す機会になる
- インターネット契約の内容確認ができる
- セット割引など料金プランの見直しができる
- 不要な引き込み線の処理について検討できる
- 利用休止や番号保管といった選択肢を知る
- 銀行やカード会社の連絡先変更を意識できる
- 請求が続いてしまう原因を確認できる
- 工事立会いの要否を契約内容で判断できる
- 家族や親族との連絡方法を見直す機会になる